ローコード開発って何ぞや?
こんにちは。開発一部 第 2 課の前田です。
ローコード開発という言葉、耳にする事があると思います。
そのローコード開発について、ざっくり紹介したいと思います。
常駐しているお客様先での、私が携わっている ETL(*)のシステムもローコードの開発ツールを採用しています。
*ETL とはデータを 抽出(Extract) 変換(Transform) 格納(Load) する一連のプロセスの事です。
ローコードツールの特徴として
- コードを書く量を最小限に抑え、GUI 等を使ってアプリを構築する手法
- テンプレートや部品化された機能を使って、ドラッグ&ドロップ操作で UI やロジックを構築
- データベースや API 連携が GUI で設定できて、コード記述が最小限で済み、SaaS や API 連携にも対応していて、外部サービスとの統合がスムーズである
(イメージ)
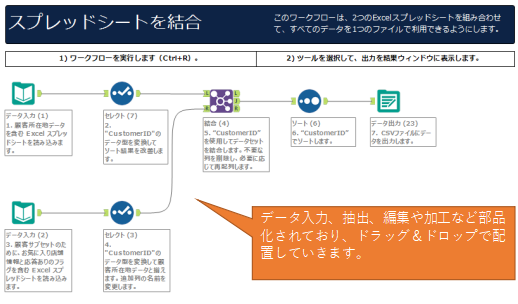
又、コンポーネント単位でデバッグが出来る事で、途中結果の確認が容易にできます。
プログラムバグが出たとしても、原因調査がしやすく特定するまでの時間が速いです。
(イメージ)
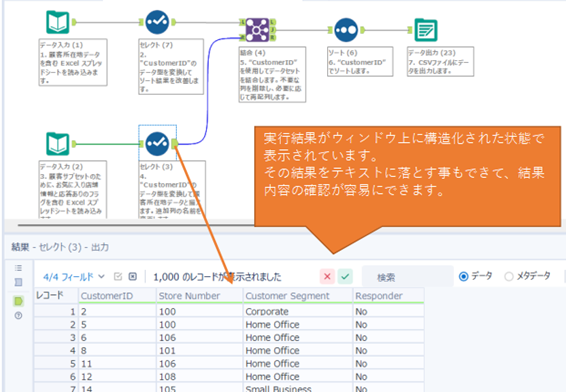
ローコード開発のメリットとデメリット
[メリット]
- 学習コストが少ない
何らかのプログラム言語を習得する必要がない(但し IT リテラシーは必要) - 開発コストが少ない
コーディング量が少ないため、短期間でリリースができる
外注せずに、社内で開発ができる
標準化されているので、後から修正がしやすく、他人が作ったソースの解析もあまり悩まなくで済むのが良いところです
[デメリット]
- ツールのライセンスや保守料等の費用が発生する
- ツールの制約によって、独自仕様の実装が難しい場合があります
- 複雑な分岐やロジックになると、結局ソースが見にくくなったり、
「あれ、こんな事はできないのね?」みたいに、プログラマ経験があると混乱する場面もたまにあります。 - IT 部門以外の方が開発すると、ポリシーが徹底されないリスクがあります
最後に
最近では AI による開発支援機能が追加されたりと、ツール自体が進化してます。
開発コストも小さいのでアジャイル開発、小規模プロジェクトには向いていると感じます。
メーカー企業では、このようなローコードで作れるアプリを導入して IT 部門だけでは無く、業務部門の中で開発する流れが進んでいるようです。